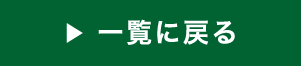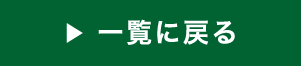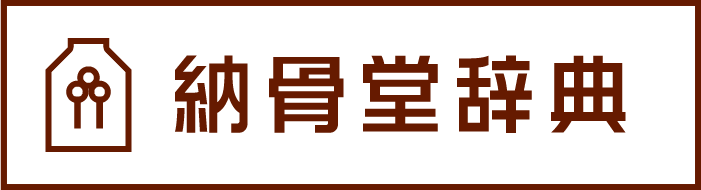雛祭りの起源は?人形の飾り方から供養の仕方まで
桃の節句には、雛人形を飾り、雛祭りを行います。雛人形は、飾って美しいばかりではなく、実は厄除けにも役立っていることをご存じでしょうか。雛祭りの起源や雛人形を飾る時期、飾りつけの仕方から供養方法までをご紹介します。

雛祭りの起源は平安時代にさかのぼる
そもそも、なぜ、誰が、いつから雛祭りを行うようになったかはわかっていません。しかし、平安時代にはすでに、貴族の子女たちが雛人形の原型となる人形で雛遊びをしていたようです。人形遊びは、現代にまで根強く残っている女の子のための遊びですよね。一方、人形には人の災厄を肩代わりできる力があると考えられ始めたのも平安の頃といわれ、厄除けとして川などへ紙で作った人形を流す「流し雛」が行われていました。江戸期になり、雛人形が広く知られるようになると、「雛人形を持てば、女性にふりかかる災厄を人形が一生肩代わりしてくれる」とされるようになり、武家などの嫁入り道具に持たせることが増えたといわれています。
雛人形を飾る時期
3月3日、桃の節句に雛祭りを行うしきたりが固まったのは、江戸時代以降のことといわれています。しかし、3月3日の1日だけ雛人形を飾るという人はあまりいないでしょう。せっかくの雛人形ですから、長く飾っておきたいところですよね。雛人形を飾る時期は、2月4日の立春を待って、暦の上での春を確認してからがよいとされます。二十四節気の一つ、「雨水(うすい)」である2月18日、または19日に飾るのがよいといわれることもあり、地域によってしきたりはさまざまです。雛人形を片付ける時期も地域によってさまざまで、「早く片付けないとお嫁に行き遅れる」とされるところもあれば、旧暦の桃の節句に合わせて4月まで飾るところもあります。
雛人形の飾り方――三段雛の場合
雛人形の飾り方の基本は、「男雛が向かって左、女雛が右」です。男雛には冠をかぶせ、笏(しゃく。棒のようなもの)を右手に持たせ、左の腰には刀を忘れずに差しましょう。女雛には、扇を手に持たせてあげます。なお、京都風で飾る場合は、男女雛の並びが逆になるので注意しましょう。一段目中央にはお神酒を置き、両脇にぼんぼりを配置して後ろに屏風を飾ります。2段目には、三人官女を並べます。座っている官女がいたら、真ん中に座らせてバランスを保ちましょう。残りの2人は、いずれかの足を前に出しているため、それで左右がわかります。向かって左から銚子、三方、長柄銚子を持たせましょう。3人の間に1つずつ、お餅を載せた高坏を飾ります。3段目には、五人囃子が並びます。向かって左から、「太鼓」「大鼓」「小鼓」「笛」「謡い手」となるよう並べましょう。
雛人形の飾り方――4段目以降
4段目には向かって左側に右大臣、右側に左大臣を並べます。左大臣が老人、右大臣が若者なので、目安としましょう。両端に人形を置いたら、お膳と菱餅を両脇に配置します。5段目には3人の仕丁(しちょう)が飾られます。三人の並びは、向かって左から「怒った人」「泣いた人」「笑っている人」です。3人を中央に配置したら、左端に橘、右端に桜を置きましょう。6段目、7段目は人形がなく、嫁入り道具だけが飾られます。お道具の位置には決まりがないため、バランスを考えて配置しましょう。
雛人形のお手入れ方法
高価な雛人形ですから、できるだけ長持ちさせたいですよね。雛人形のお手入れで一番大事なのは、天気が良く乾燥した日に片づけることです。湿気はカビを呼んでしまうためです。また、箱のなかには防虫剤を入れておきましょう。それができたら、人形のお手入れは細かなハタキや筆でほこりを払う程度です。人形はとても繊細ですから、汚れがあるからといって強くこすってはいけません。手の脂がつかないよう手袋をして扱い、人形や道具は一つずつティッシュにくるんでホコリを防ぎましょう。壊れている箇所があれば、人形の修理業者に相談してみるのがおすすめです。
雛人形の処分方法
飾らなくなった雛人形を、どう処分するか悩んでいる人もいることでしょう。一般ごみとして処分する気にはなかなかなれませんよね。人形供養をしてくれるお寺は近くにありませんか。ぬいぐるみだけでなく、雛人形も供養してくれます。受付時期が限られているお寺もありますから、注意しましょう。もし、人形供養をしてくれる場所が近くに見当たらない場合は、供養する人形の郵送を受け付けているお寺や、全国ネットで人形供養を行っている業者に依頼することができます。まずは相談してみましょう。
まとめ
以上、雛祭りの起源や雛人形を飾る時期、飾り方、お手入れ方法、処分方法までをお伝えしました。女の子が生まれて、これから雛人形を買いたいと思っている人もいることでしょう。あらかじめお手入れ方法や手放し方を知っておくと、のちのち困りません。平安から続く日本の伝統行事を、ていねいに受け継いでいきましょう!
関連記事:針供養って?ロボット供養、靴供養など他にもあるいろんな供養をご紹介
▽当サイトではおすすめの樹木葬ランキングや自然葬や永代供養墓についても解説しています。是非ご参照ください。>>樹木葬辞典|樹木葬の総合情報サイト
あわせて読みたい

長い人生の中で、誰しも経験する「死別による悲嘆」。その悲しみは心だけでなく、体までもむしばみ、生活に支障をきたす場合があります。もし、自分や周りの人がそうなった時、どのように支え合い、克服すればいいのでしょうか?そこで注目されているのが「グリーフケア」です。グリーフケアとは大切な人との死別による悲嘆のプロセスにおいて、立ち直りまで寄り添い、サポートする方法です。お墓の存在も故人の死を受け入れると意味で、大切なグリーフケアの1つです。いつか来るその日のために、今回はグリーフケアについてご紹介します。

近年の少子高齢化や首都圏への人口集中などにより、お墓を巡る環境が激変しています。住居の都合で故郷にある先祖代々の墓守が難しい、子どもがいないなどの理由で、お墓の継承者がいずれ途絶えるのは明白な家庭も増えてきました。そのまま放置しておくと先祖代々のお墓は無縁墓となり、墓地から墓石ごと撤去されてしまいます。そのため、「墓じまい」をしたり、先祖代々のお墓を「永代供養」の墓へ改葬するなどを行う人が年々増加しています。今回は「墓じまい」や「永代供養」をお考えの方に向けて、「墓じまい」や「永代供養」とはどういったものなのか、その違いなどについて紹介します。

永代供養とは、お墓参りや供養をする身内(縁故者)がいなくなり、無縁仏となってしまうことを避けるために、寺院などの管理機関が責任を持って永代にわたって供養することを指します。しかし最近では、将来、身内(子どもなど)に墓守りの心配や負担をかけたくないという理由から、生前に永代供養の申し込みをする方も少なくありません。永代供養の費用や期間について詳しく見ていきましょう。

仏壇には位牌がつきものです。仏壇に向かってお参りするとき、「位牌に向かってお参りしなさい」と教わってきた人も多いでしょう。しかしこの位牌が、何を意味するのかを知っているでしょうか。ここでは位牌の意味と、その種類について紹介します。

「秋になると報恩講の行事やお祭りを行っているお寺を見かけるけれど、これって何?」「『報恩講(お取越)のご案内』という葉書が来たけれど、参加しなければならないの?」などと疑問を感じている人はいませんか。報恩講は、浄土真宗の行事です。浄土真宗の宗祖である親鸞の命日を中心に営まれる報恩講について、詳しく解説します。