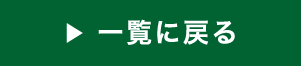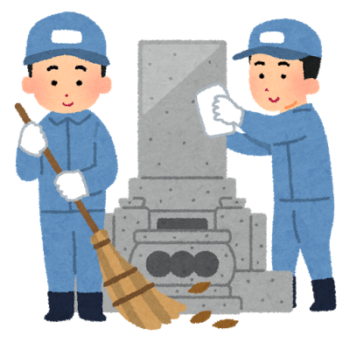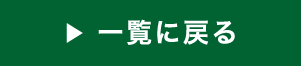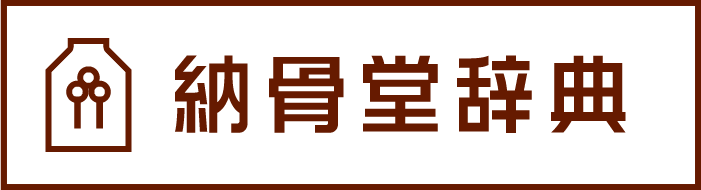エコ葬とは?火葬時のCO2削減で死後も環境保護のメッセージを
エコ葬という言葉を知っていますか?エコ葬とは自然環境に配慮した葬儀のことを指します。葬儀とエコロジー、全く関連がないと思いがちですが、葬儀で地球環境保護の手助けができるのなら素敵だと考える人は多いでしょう。葬儀社の提案するエコ葬から喪主が自分でできるエコ葬、さらに世界のエコ葬について解説します。

エコ葬とは?
環境保護というと、化学物質による自然環境の汚染を防いだり、動植物を保護したり、植林をしたりなど、さまざまな活動が思い浮かびます。そのなかでエコ葬が注目するのは、とくに地球温暖化の原因となるCO2の削減です。火葬時には大量のCO2が排出され、その量は人ひとりが1年間に排出するCO2と同程度と言われています。私たちは死亡すると、環境破壊のもととなる化学物質を残していってしまうということです。生前、なるべくエコな(環境にやさしい)暮らしをと心掛けてきた人にとっては、耐え難いことではないでしょうか。エコ葬とは、できる限り環境に負荷をかけないための葬儀プランなのです。
エコ葬1:段ボール製のエコ棺でCO2削減
火葬が行われる際、遺体の燃焼時のCO2量を削減するのは不可能なので、せめて棺のぶんだけでもCO2の削減をしようというのが、多くの葬儀社が取り組む「エコ葬」の内容です。一般的な棺は、桐やヒノキ、モミの木などでできており、合板製が主流です。木でできた棺を燃焼させると、当然のことながらCO2が大量に発生します。しかし、木でできた棺の代わりに強化段ボールを組み合わせた紙製の棺を使えば、排出されるCO2量は大幅に減少します。段ボール製の「エコ棺」を開発したウィルライフ社によると、合板製の棺に比べて燃焼時のエネルギー量は約50%削減され、燃焼時の有害ガスは1/3以下になるとのことです。
参考文献:「エコ+コフィン」環境にやさしいエコ棺 エコフィン[ノア]
エコ葬2:寄付金付きで植林活動ができるエコ棺
エコ棺の利点は、燃焼時のエネルギー量や有害ガスの減量のみにとどまりません。合板製の棺を使わないということは、森林資源を大事にすることにつながっています。合板製の棺は、多くが世界各地の森林を伐採して作られているためです。段ボールも木材から作られますが、使う木材の量は合板製の2/3程度で済むといわれています。さらにエコ棺を購入すると、使用した森林資源分を植林するための寄付金がついています。自分が使った分の木材を次世代に還す仕組みがついているのが、エコ棺なのです。
エコ葬3:二酸化炭素の出ないドライアイスやハイブリッド車を使う
エコ棺を使う以外にも、エコな(環境にやさしい)工夫をしている葬儀社はあります。例えば、遺体保全にはドライアイスが使われますが、このドライアイスからもCO2は発生します。ドライアイスを再利用可能な保冷材に替えることで、エコへの取り組みをしている葬儀社があります。なお自動車の排気ガスを減少させるハイブリッド車の内燃機関を持つ霊柩車が登場しています。まだまだ導入している葬儀社は少ないですが、エコでクリーンなイメージから、今後街中で目立つようになるかもしれません。
エコ葬4:喪主ができる環境配慮

みなさんが地球環境に配慮したいと考えたときに、喪主側のほうでできるエコもあります。例えば、副葬品の減量や内容への配慮です。棺の中に入れる副葬品は、故人を想えばこそ量が多くなってしまいがちですが、そのぶんやはりCO2量は多くなってしまいます。なお、うっかり燃えないもの(燃やしてはいけないとされるもの)を入れてしまうと、有害ガスが発生してしまう恐れもあるのです。棺には、木製のゴルフクラブなど副葬品用に開発された小物を入れたり、ゆかりのものを撮影して写真だけを入れたりすれば、環境保護に貢献できるでしょう。なお、香典を環境保護団体に寄付するというのも、喪主ができる取り組みの一つです。参列者には、香典返しの代わりに寄付を受けた団体からのお礼状を差し上げるという仕組みも生まれています。
エコ葬5:スウェーデンのフリーズドライ葬
世界のエコ葬としては、スウェーデンの研究者が開発した「フリーズドライ葬」が挙げられます。遺体を凍らせ、土に還る素材の棺に納めた後、液体窒素に浸して完全に凍結させるのです。それから機械振動により、粉末状にします。これを地中に埋めて土に還すのが、フリーズドライ葬です。まだまだスウェーデンでも実用化に至っているとはいえないため、日本に上陸するのはいつになるか分かりません。しかし、火葬によるCO2が排出されることなく、確実に土にかえることができるエコ葬として注目を集めています。
エコ葬まとめ:自分の死後もエコロジーの意思表示を
以上、エコ葬について解説しました。環境保護活動に力を尽くしているという人はもちろん、死してなおCO2を排出することで環境破壊をしてしまうことに悔しさを覚える人は、エコ葬を考えてみても良いのではないでしょうか。葬儀は、自分の意思表示ができる最後の場です。エコロジーの意思表示を参列者に伝えたいという人は、エコ葬のプランがある葬儀社を探してみましょう。
当サイトではおすすめの樹木葬ランキングや自然葬や永代供養墓についても解説しています。是非ご参照ください。>>樹木葬辞典|樹木葬・自然葬・永代供養墓を解説
あわせて読みたい

「墓じまい」という言葉を知っていますか。墓じまいとは、代々継いできたお墓を閉じてその土地を更地にして墓地管理者に返却することを言います。少子高齢化が進み、年々死亡者数が増えている昨今、お墓の承継者が足りなくなり墓じまいをしてお墓を閉じる人が増えています。その理由は、今の住まいから遠く離れた場所にある先祖のお墓を管理することが物理的に難しくなってしまった、または、お墓を受け継いだものの後継者がいないといったものが主です。墓じまいと関連して、遺骨を別の場所に移す改葬をすることでお墓の管理を楽にしようという人もいます。このように関心が高まりつつある「墓じまい」や別のお墓に遺骨を埋葬し直す「改葬」について手順と注意点をお伝えします。

直葬とは、通夜式とお葬式がなく火葬だけを行う簡素な葬儀形式のことを言います。今、都市部ではおよそ2割から3割ほどの遺族が直葬を選んでいると言われています。通夜式とお葬式を行わない、というと、「それでいいのだろうか」と疑問に思う人もいるでしょう。直葬について詳しく解説します。

お墓といえば、家族でどなたかが亡くなった際に準備するというイメージの方が多いかもしれません。しかし、現在は終活を行い自分のお墓を生前に購入する方も増えてきています。その背景には、お墓の継承者問題や少子化問題など深刻な問題が見え隠れしていますが、お墓の生前購入をすることにはメリットがあるようです。

合祀墓(ごうしばか)とは、一つの場所に複数の人の遺骨を一緒にして供養を行うお墓を指します。合葬墓(がっそうぼ)、合同墓などといった呼ばれ方をされることもあります。

後継者がいないために先祖代々のお墓を更地にし、管理者へ墓地を返還することが「墓じまい」と呼ばれるようになりました。今あるお墓を無縁墓化させないためには、これから家族の形がどうなっていくのかを正確に予想し、早めに決断をすることが大切です。墓じまいで後悔しないためにはどうすれば良いか、そのポイントをお知らせします。